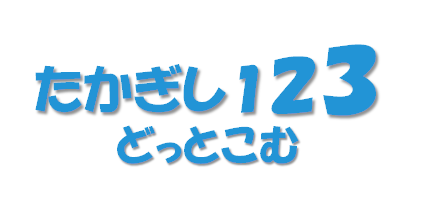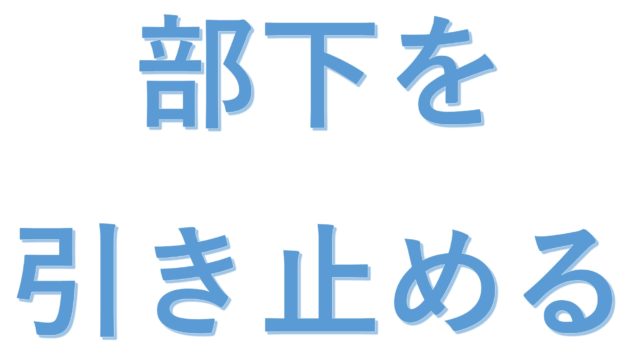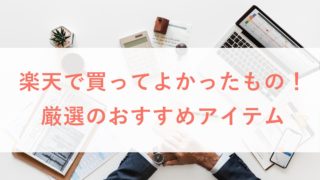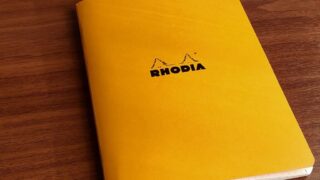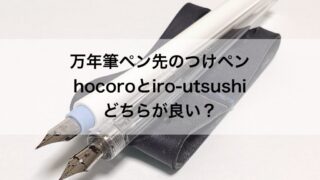内容は同じでもデザイン一つでわかりやすさも印象もまるで違います。
デザインの大事さはわかるものの、実際に自分がやろうとしてもどうして良いかわからない・・・。
結局センスじゃない? てな感じで半ばあきらめでした。
当ブログのデザインも褒めていただくことが多いのですが、有料のテンプレートを利用しているためで自分で位置から組んだわけではありません。お金の力に頼っただけです。
そんな折、SNSで『伝わるデザインの基本』という本がとてもわかりやすく、ブログのデザインにもおすすめとのことで興味を惹かれて購入しました。
(2025/07/15 00:40:09時点 Amazon調べ-詳細)
本を購入してからパラパラと見たくらいでしばらく放置していたら、先日たまたま社内のチーム対抗のプレゼン発表会でチームの発表担当になってしまいました。
(一応自分から立候補したのですが、積極的にやりたいというよりはチームの比較的古いメンバーかつ若めということで仕方なく・・・)
最近のこの発表会では資料のデザインにもしっかり力を入れているチームが多く、私のセンスでこのまま臨むとヤバイということで本の存在を思い出して、読みながらパワポ資料を作ってみました。
その結果、なかなかの高評価で資料のみやすさを褒めていただくことがかなり多く、ポイントによる総合評価でも上位に僅差の第3位でした!
今まで仕事上の資料のデザインについて褒められた経験はなかったので、ホッとするとともにとても嬉しい結果になりました。
という訳で、デザインに自信のない方にこの本はとてもおすすめです!
『伝わるデザインの基本』で学んだこと
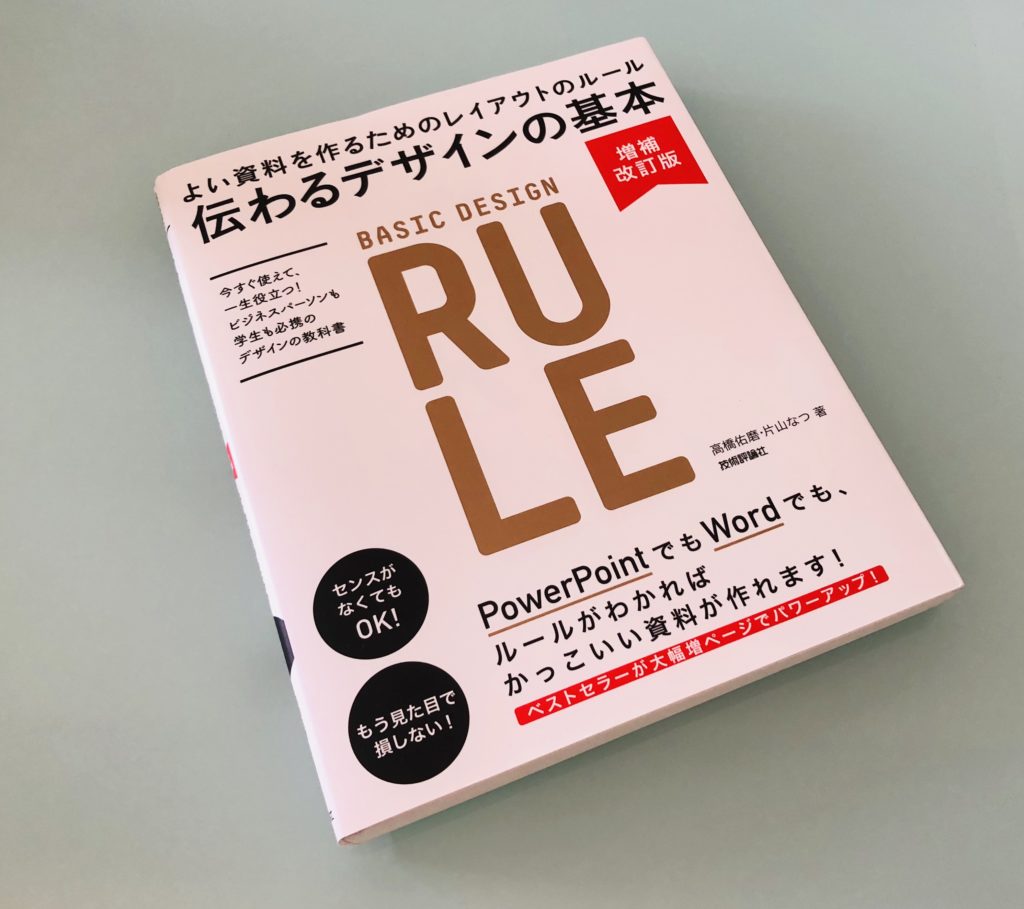
伝わるデザインの資料作りのポイントがよくわかるので、資料を取り入れていけば自然とデザインが良くなっていきます。
その中でも資料作りのときに特に意識したこと・学んだことは大きく以下の3点です。
- デザインの統一性
- 見やすいフォント
- 細かいところにこだわる
デザインの統一性
デザインの統一性なんて、パワポだとテンプレートを使うことで自然とスライド間の統一感が出るくらいのものだと思って全く意識していませんでした。
これが全くのダメダメ。
今回は文字のフォントから見出しの大きさ、枠の丸め具合、図形や文字の色、文字の余白の取り方などすべて統一しました。
色についてもルールを決めて、文字色は基本は濃いグレーで強調色はオレンジ、背景色は青に統一。
統一感があることで資料が自然と美しく見えるのと、色使いも少なくしたことでゴチャゴチャとせず見やすくなりました。
デザインは図解力によるところが大きいものだと誤解していました。
図解力についてはまだまだで、できあがった資料も割とシンプルな見た目なのですが、ルールを決めて統一感を出す効果はかなり大きかったように思います。
これをするだけでも資料の印象はガラッと変わります。
見やすいフォント
フォントといえば「ゴシックとかメイリオあたりを使っておけば親しみやすい感じで良いんじゃない?」くらいにしか思っていなかったのですが、資料の場面に応じて使い分けが必要なことを学びました。
フォントは奥が深いですね~。
太字(ボールド)にしたときの美しさが違うとか全く知らなかった。
今回の資料では『游ゴシック』を使用しました。
判読性が高く、太字でも見やすく、英数字と日本語が混ざっても読みやすいとのことで、実際すっきりと読みやすくポップになりすぎていない印象です。
細かいところにこだわる
余白を取るとか、見出しの開始位置と本文の開始位置を合わせるとか、見やすくするために様々な要素があります。
1つ1つは細かいなーとは思うのですが、それらが組み合わさって全体的な見やすさが決まるので、手を抜いてはいけないところでした。
めんどくさがりなので、オブジェクトをコピーしたあとにちょこっと直したときなんかはサボって他のものには反映せず形がバラバラなんてこともよくありました。
1点目にあげたデザインの統一性にも通ずるところではあるのですが、こういう細かいところにこだわれるかどうかで大きな違いが出るという気づきでした。
『伝わるデザインの基本』のまとめ

デザインをセンスではなく、理論的に解説してくれるので、自分にはセンスが無いと諦めてしまっている方には特に手にとってみていただきたい良書です。
オフィス文書(Word、PowerPointなど)については具体的な設定方法も解説してくれているので、オフィスを使っている方なら活用しやすいのも良いところです。
(2025/07/15 00:40:09時点 Amazon調べ-詳細)